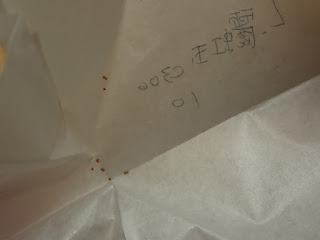1月16日
Echium wildpretii(ムラサキ科)とFerraria crispa(アヤメ科)です。その後は新たな発芽個体はなく、それぞれ3個体と4個体です。
Echium wildpretiiは先に発芽した2個体の本葉が4枚、後から発芽したものは2枚です。Ferraria crispaは1枚葉のみを展開しています。
1月29日
Echium wildpretiiは、先に発芽した2個体の本葉が5枚、後から発芽したものは3枚です。最初に発芽した個体は双葉が枯れました。Ferraria crispaは2個体で2枚目の葉が伸び始めました。
2月からは約1週間に1回、液肥(ハイポネックス)を1000倍希釈程度で与え始めました。
3月7日
Echium wildpretiiはかなり成長しました。本葉数は9~11枚で、脇芽も発生しています。個体サイズは発芽日に関わらずほぼ同じです。そして、後に発芽した個体のみ双葉が残っています。
幼個体への施肥は控えるべきと考えていましたが、序盤から肥料を与えた方がよく成長するようです。
一番大きな葉は、葉柄を入れて長さ4 cmくらい。表裏に毛が密に生えています。
昼間は葉を水平に広げ、夜になると直立させます。これは、新芽を夜間の霜害から保護するための戦略なのかもしれません。
Ferraria crispa4個体の葉の枚数は、3、2、1、1枚です。
1個体は葉が枯れ始めました。
本種は冬型(秋から春に展葉し、夏は休眠)の植物なので、そろそろ休眠に入るのだと思います。
2020年3月7日土曜日
2020年2月6日木曜日
リトープスとコノフィツム 播種から56日目
1月29日
コノフィツムとリトープスを播種してから約2カ月が経ちました。
前回(12月28日)の報告以降での新規の発芽はありません。
各種ともかなり大きくなりました。数字上は前回からの変化が小さいですが、前回はしっかり計測したわけではなく、過大評価していたかもしれません。
播種から約1ヶ月間は腰水状態を維持していましたが、現在は水やり頻度を5日~1週間/回に落としており、1,2日間土の表面が乾いた状態になります。とはいっても湿った時間が長いためか、土の表面にはコケ(蘚類)が発生しています。
Conophytum burgeri
ブルゲリは直径1.5 mm強になりました。
1個体が枯れ、現在4個体です。
光を浴びると表皮細胞がキラキラと輝き、宝石のようです。
Conophytum christiansenianum
直径2.5mmくらいです。個体数は5個体のままです。
Conophytum ornatum
直径1.5~3mmくらいです。アルビノの2個体が枯れ、現在5個体です。
麗虹玉 Lithops dorotheae
直径1.5~3mmくらいで個体差が大きいです。個体数は10のままです。
2020年1月30日木曜日
2020年1月 ヘリアンフォラの様子
2020年1月18日
2018年6月頃から栽培しているヘリアンフォラHeliamphora sp.です。
用土が劣化してきたので、昨年の初秋に株分けを植え替えを行いました。
半密閉状態で栽培しています。
大きな株の方。
素焼き鉢に川砂:ピートモス=約7:3で、腰水状態で栽培しています。葉の先端のネクタースプーンが発達し、調子は良さそうです。
購入時の鉢に植え付けた、小さな株。こちらも少しずつ大きくなっています。
ネクタースプーンからあふれる蜜。
2018年6月頃から栽培しているヘリアンフォラHeliamphora sp.です。
用土が劣化してきたので、昨年の初秋に株分けを植え替えを行いました。
半密閉状態で栽培しています。
大きな株の方。
素焼き鉢に川砂:ピートモス=約7:3で、腰水状態で栽培しています。葉の先端のネクタースプーンが発達し、調子は良さそうです。
購入時の鉢に植え付けた、小さな株。こちらも少しずつ大きくなっています。
ネクタースプーンからあふれる蜜。
2020年1月2日木曜日
Echium wildpretiiとFerraria crispa 播種から50日目
12月28日
Echium wildpretiiの実生です。11月9日に播種してから50日経ちました。
大きな個体は発芽から約40日、小さな個体は約30日です。大きな個体は本葉が4枚出ました。
12月26日に新たに1粒発芽しました。これで、播種した6粒中3粒が発芽したことになります。
こちらはFerraria crispaの実生です。4個体で変わりありません。
発芽から約20日~35日経ち、葉が大分伸びました。最初に発芽した個体は2枚目の葉が出始めています。
Echium wildpretiiの実生です。11月9日に播種してから50日経ちました。
大きな個体は発芽から約40日、小さな個体は約30日です。大きな個体は本葉が4枚出ました。
12月26日に新たに1粒発芽しました。これで、播種した6粒中3粒が発芽したことになります。
こちらはFerraria crispaの実生です。4個体で変わりありません。
発芽から約20日~35日経ち、葉が大分伸びました。最初に発芽した個体は2枚目の葉が出始めています。
2020年1月1日水曜日
リトープスとコノフィツム 播種から24日目
12月28日
5日に播種してから24日経ち、コノフィツム3種(C. burgeri, C. christiansenianum, C. ornatum)とリトープス1種(麗虹玉L. dorotheae)の発芽はおおむね完了したようです。
播種したタネと名札が食い違っており、現時点では発芽個体の正確な種名が分かりませんが、恐らく…
・C. burgeri 6粒中5粒(発芽率83%)
・C. christiansenianum 10粒中5粒(同50%)
・C. ornatum 10粒中7粒(同70%)
・L. dorotheae 11粒中10粒(同91%)
です。まあまあの発芽率かな、と思います。
発芽個体の成長段階は、まだ子葉(双葉)が出そろったところですが、早くも各種の特徴が出始めています。
C. burgeriの実生。室内で育てているため、周りに埃が落ちて少々見苦しいですが…
実生のサイズは1ミリ強と小さく、芽生えらしからぬ姿をしています。恐らく、子葉は合着しているのだと思います。
恐らくC. christiansenianumの実生。C. ornatumの可能性あり。
実生のサイズは2~2.5ミリくらい。子葉は合着しているものの中央に裂け目が入り、幾分双葉らしさが残っています。
恐らくC. ornatumの実生。C. christiansenianumの可能性あり。
実生のサイズは1.5~2.5ミリくらい。形状はブルゲリとの中間的な雰囲気です。
アルビノのC. ornatum?の実生。
7個体中3個体が白色もしくは薄緑色で、葉緑体を一部、もしくは完全に欠いていると思われます。
恐らく光合成能を欠いており、今後の成長は厳しいかもしれません。
麗虹玉L. dorotheaeの実生。
実生のサイズは2~2.5ミリくらい。子葉は合着しているものの裂け目があり、双葉らしさが残っています。コノフィツム3種と比べると、「普通の芽生え」の雰囲気があります。また、表皮細胞が小さいためか、表面が滑らかにみえます。
5日に播種してから24日経ち、コノフィツム3種(C. burgeri, C. christiansenianum, C. ornatum)とリトープス1種(麗虹玉L. dorotheae)の発芽はおおむね完了したようです。
播種したタネと名札が食い違っており、現時点では発芽個体の正確な種名が分かりませんが、恐らく…
・C. burgeri 6粒中5粒(発芽率83%)
・C. christiansenianum 10粒中5粒(同50%)
・C. ornatum 10粒中7粒(同70%)
・L. dorotheae 11粒中10粒(同91%)
です。まあまあの発芽率かな、と思います。
発芽個体の成長段階は、まだ子葉(双葉)が出そろったところですが、早くも各種の特徴が出始めています。
C. burgeriの実生。室内で育てているため、周りに埃が落ちて少々見苦しいですが…
実生のサイズは1ミリ強と小さく、芽生えらしからぬ姿をしています。恐らく、子葉は合着しているのだと思います。
恐らくC. christiansenianumの実生。C. ornatumの可能性あり。
実生のサイズは2~2.5ミリくらい。子葉は合着しているものの中央に裂け目が入り、幾分双葉らしさが残っています。
恐らくC. ornatumの実生。C. christiansenianumの可能性あり。
実生のサイズは1.5~2.5ミリくらい。形状はブルゲリとの中間的な雰囲気です。
アルビノのC. ornatum?の実生。
7個体中3個体が白色もしくは薄緑色で、葉緑体を一部、もしくは完全に欠いていると思われます。
恐らく光合成能を欠いており、今後の成長は厳しいかもしれません。
麗虹玉L. dorotheaeの実生。
実生のサイズは2~2.5ミリくらい。子葉は合着しているものの裂け目があり、双葉らしさが残っています。コノフィツム3種と比べると、「普通の芽生え」の雰囲気があります。また、表皮細胞が小さいためか、表面が滑らかにみえます。
2019年12月31日火曜日
コノフィツムとリトープス 播種~発芽
12月5日
コノフィツム(Conophytum)3種とリトープス(Lithops)1種のタネを蒔きました。あるびの精肉店さんから購入しました。
これまで栽培してきたメセン類は日輪玉(Lithops aucampiae)のみで、播種は初めての経験です。
種類は…
・C. burgeri (ブルゲリ) 6粒
・C. christiansenianum (シノニムのC. bilobumの園芸名は”光源氏”らしい) 10粒
・C. ornatum 10粒
・L. dorotheae (麗紅玉) 10粒
麗紅玉のタネ。大きさは1 mmくらい。
ブルゲリのタネ。麗紅玉よりも一回り小さいです。他2種のコノフィツムのタネは麗紅玉と同じくらいのサイズだったので、ブルゲリのタネの小ささは際立っています。
鉢は市販のスリット鉢を使用しました。
用土は川砂3~4:小粒赤玉土5~6:黒土1 です。
表面には赤玉土の微塵(ふるい分けした際に得た)と川砂を混合したものを薄くかけました。微細なタネが土の隙間に落ちるのを防ぐのと、タネの吸水を容易にするのが目的です。
ネット上の播種方法を参考にし、腰水管理にしました。熱湯や薬品による消毒を勧める情報もありますが、今回は特に処理していません。
12月12日
L. dorotheae (麗紅玉)?
発芽し始めました。「?」としたのは、種名を書いた札を差し間違え、現状では正確な種名が分からないからです…
C. ornatum ?
コノフィツム(Conophytum)3種とリトープス(Lithops)1種のタネを蒔きました。あるびの精肉店さんから購入しました。
これまで栽培してきたメセン類は日輪玉(Lithops aucampiae)のみで、播種は初めての経験です。
種類は…
・C. burgeri (ブルゲリ) 6粒
・C. christiansenianum (シノニムのC. bilobumの園芸名は”光源氏”らしい) 10粒
・C. ornatum 10粒
・L. dorotheae (麗紅玉) 10粒
麗紅玉のタネ。大きさは1 mmくらい。
ブルゲリのタネ。麗紅玉よりも一回り小さいです。他2種のコノフィツムのタネは麗紅玉と同じくらいのサイズだったので、ブルゲリのタネの小ささは際立っています。
鉢は市販のスリット鉢を使用しました。
用土は川砂3~4:小粒赤玉土5~6:黒土1 です。
表面には赤玉土の微塵(ふるい分けした際に得た)と川砂を混合したものを薄くかけました。微細なタネが土の隙間に落ちるのを防ぐのと、タネの吸水を容易にするのが目的です。
ネット上の播種方法を参考にし、腰水管理にしました。熱湯や薬品による消毒を勧める情報もありますが、今回は特に処理していません。
12月12日
L. dorotheae (麗紅玉)?
発芽し始めました。「?」としたのは、種名を書いた札を差し間違え、現状では正確な種名が分からないからです…
C. ornatum ?
2019年12月19日木曜日
2019年11月~12月 Ferraria crispa (starfish lily) 栽培①
11月9日
あるびの精肉店さんでFerraria crispaの種子を購入しました。
本種はアヤメ科の多年草で、南アフリカ原産です。西オーストラリアなどでは帰化植物になっているようです。
花は多肉ガガイモ類を思わせる独特なもの(Google画像検索)で、英名のstarfish lily (ヒトデのユリ)も花姿に由来しています。花香はやや不快なものらしく、ポリネーター(送粉者)もガガイモ類と同様にハエ類だそうです。
11月25日
同時に播種したEchium wildpretii(記事へのリンク)に遅れること約1週間で発根。
12月4日
種子の脇から芽が出てきました。
種の殻を被ったままだったのでうまく育つか少々不安でしたが、杞憂だったようです。
12月11日
葉が伸びてきました。子葉なのか本葉なのかは未確認です。
12月19日時点で6粒中4粒が発芽しています。
あるびの精肉店さんでFerraria crispaの種子を購入しました。
本種はアヤメ科の多年草で、南アフリカ原産です。西オーストラリアなどでは帰化植物になっているようです。
花は多肉ガガイモ類を思わせる独特なもの(Google画像検索)で、英名のstarfish lily (ヒトデのユリ)も花姿に由来しています。花香はやや不快なものらしく、ポリネーター(送粉者)もガガイモ類と同様にハエ類だそうです。
11月25日
同時に播種したEchium wildpretii(記事へのリンク)に遅れること約1週間で発根。
12月4日
種子の脇から芽が出てきました。
種の殻を被ったままだったのでうまく育つか少々不安でしたが、杞憂だったようです。
12月11日
葉が伸びてきました。子葉なのか本葉なのかは未確認です。
12月19日時点で6粒中4粒が発芽しています。
登録:
投稿 (Atom)